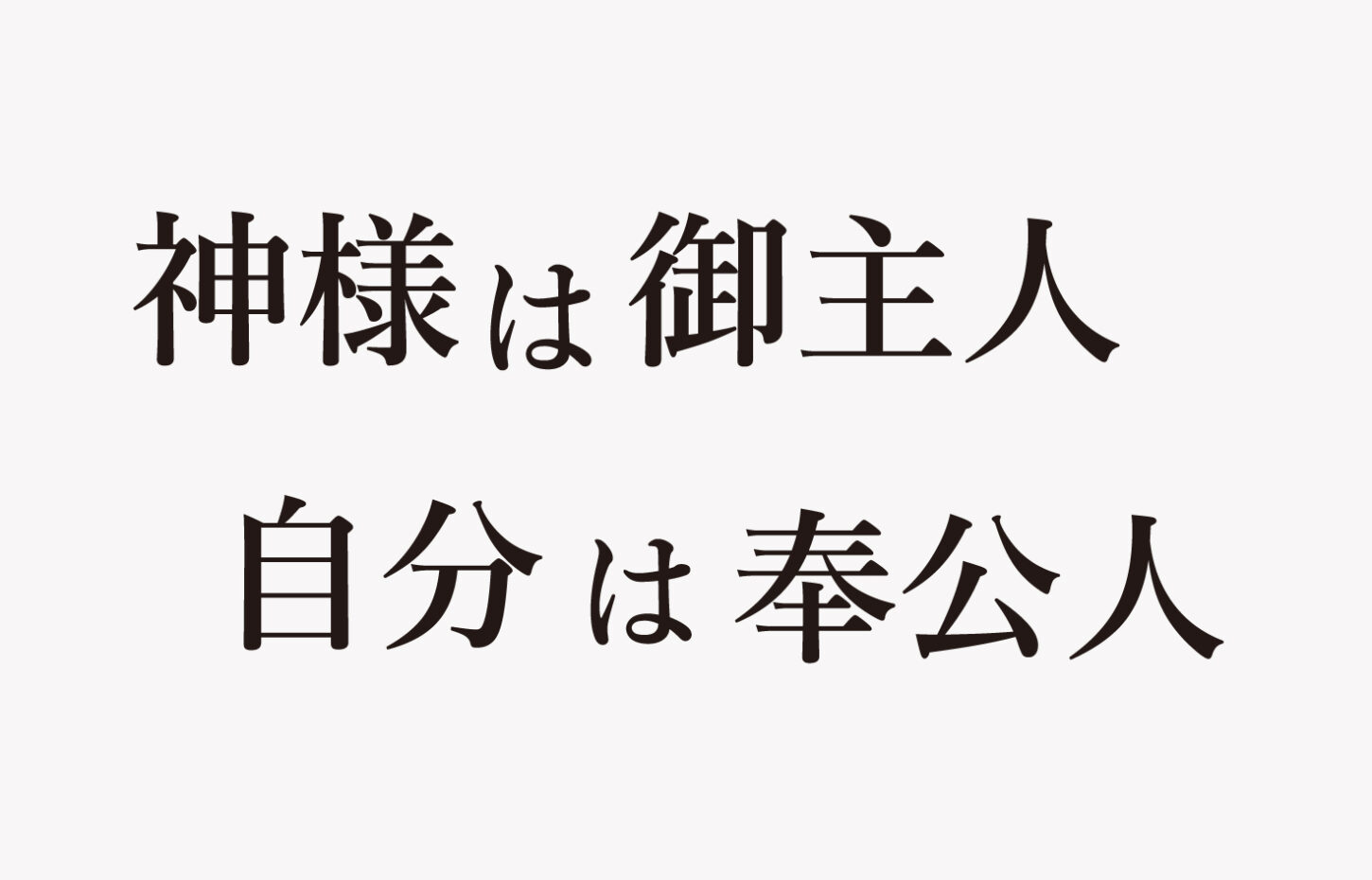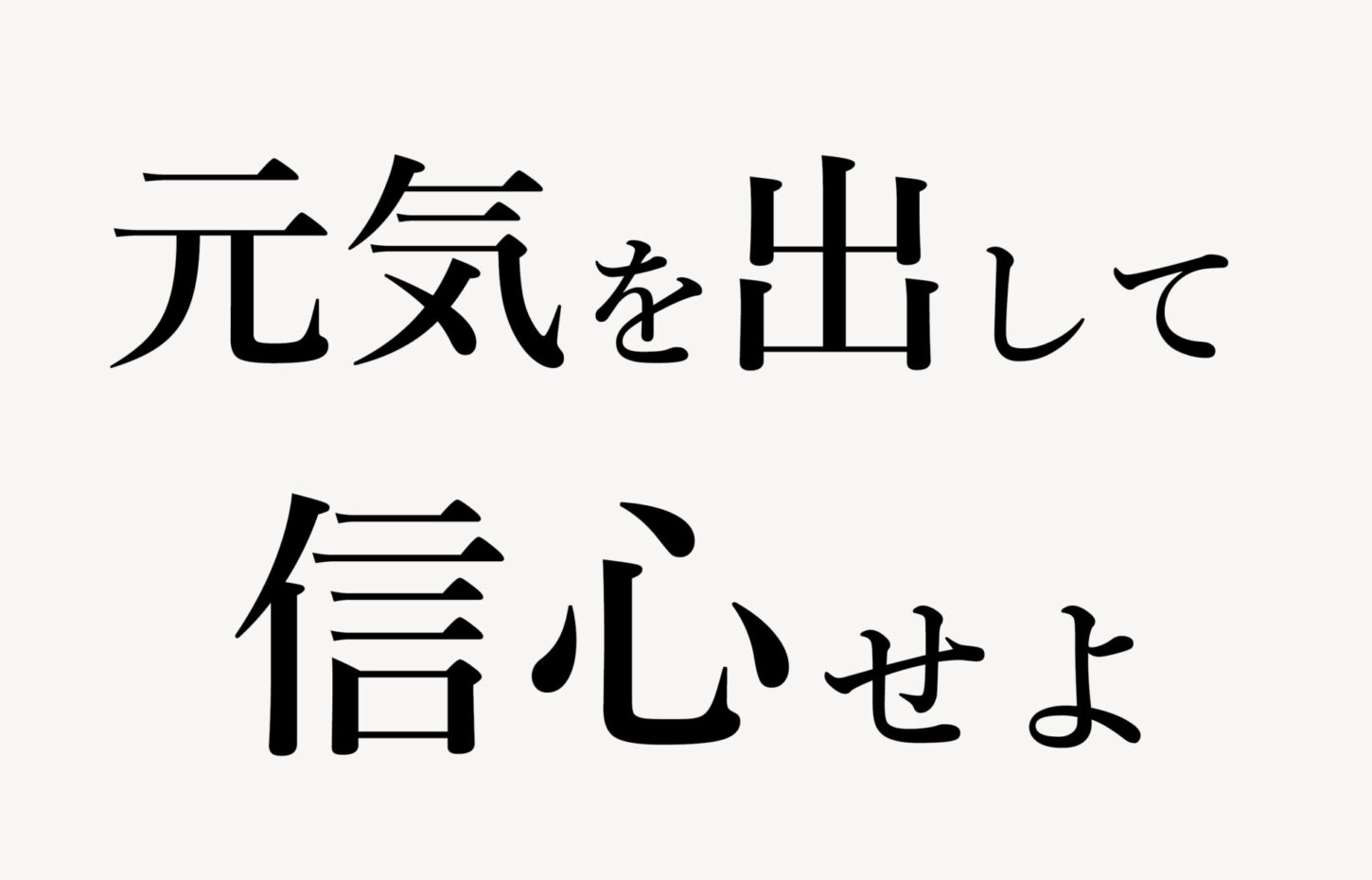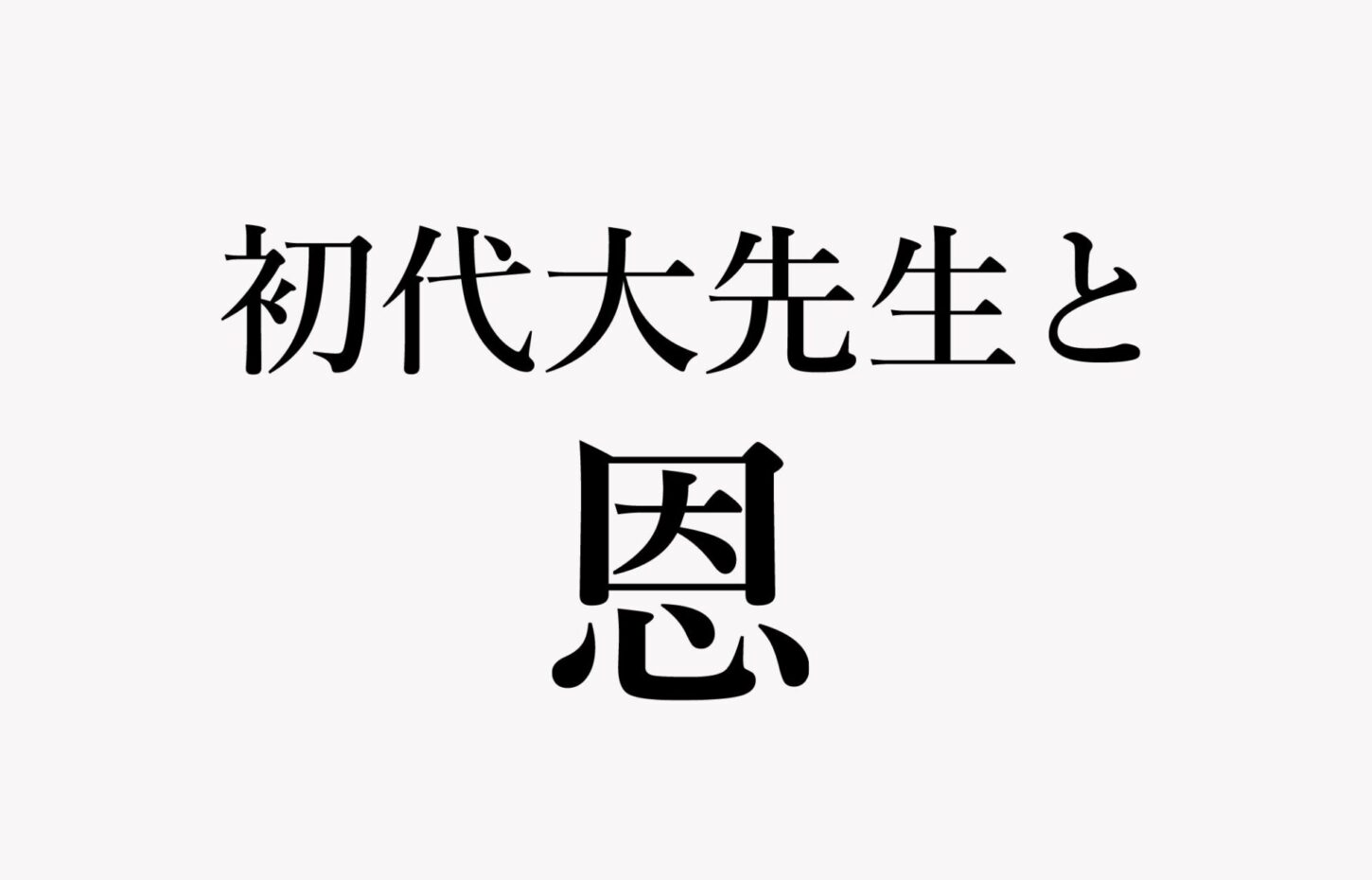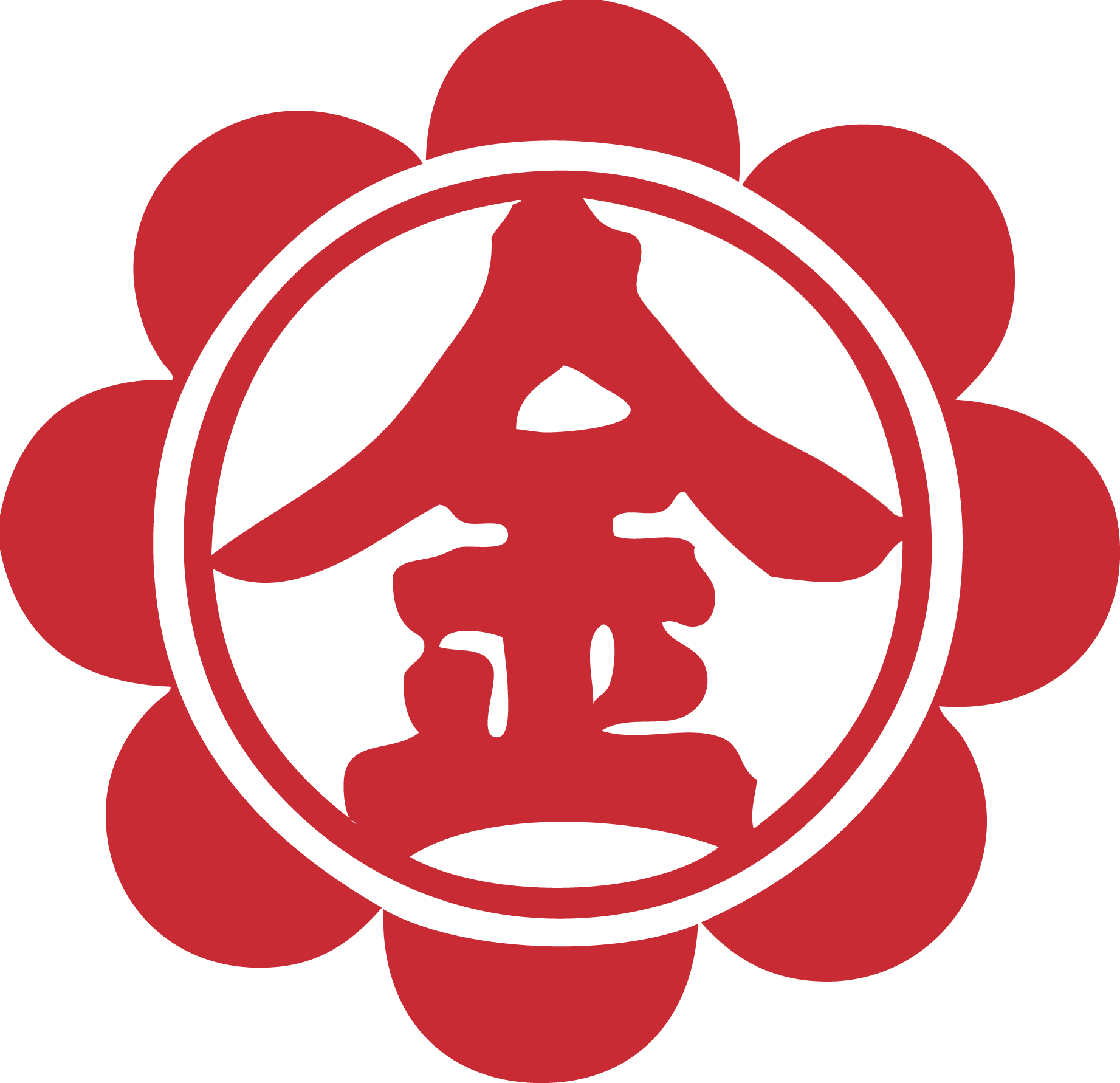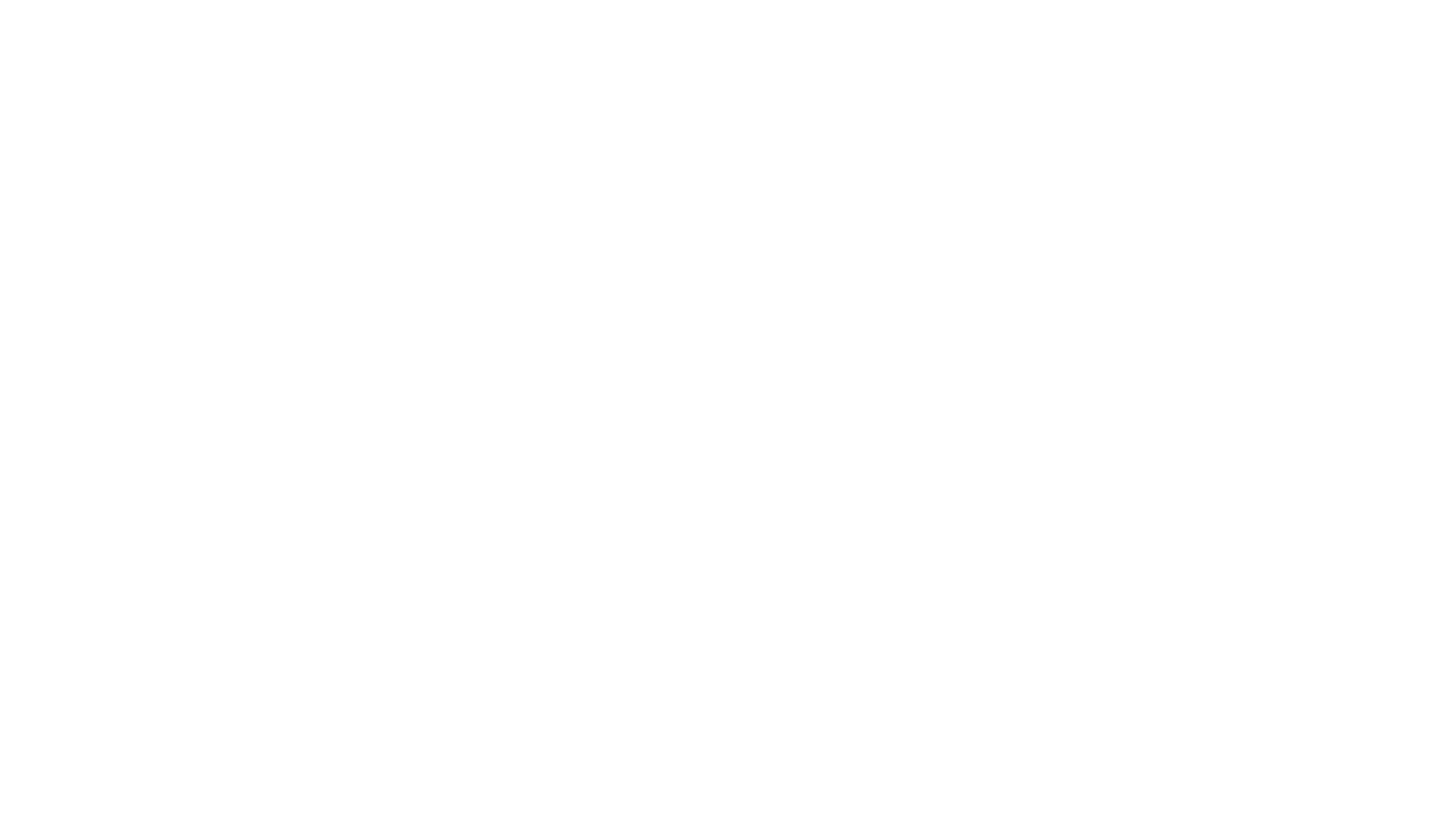物乞い
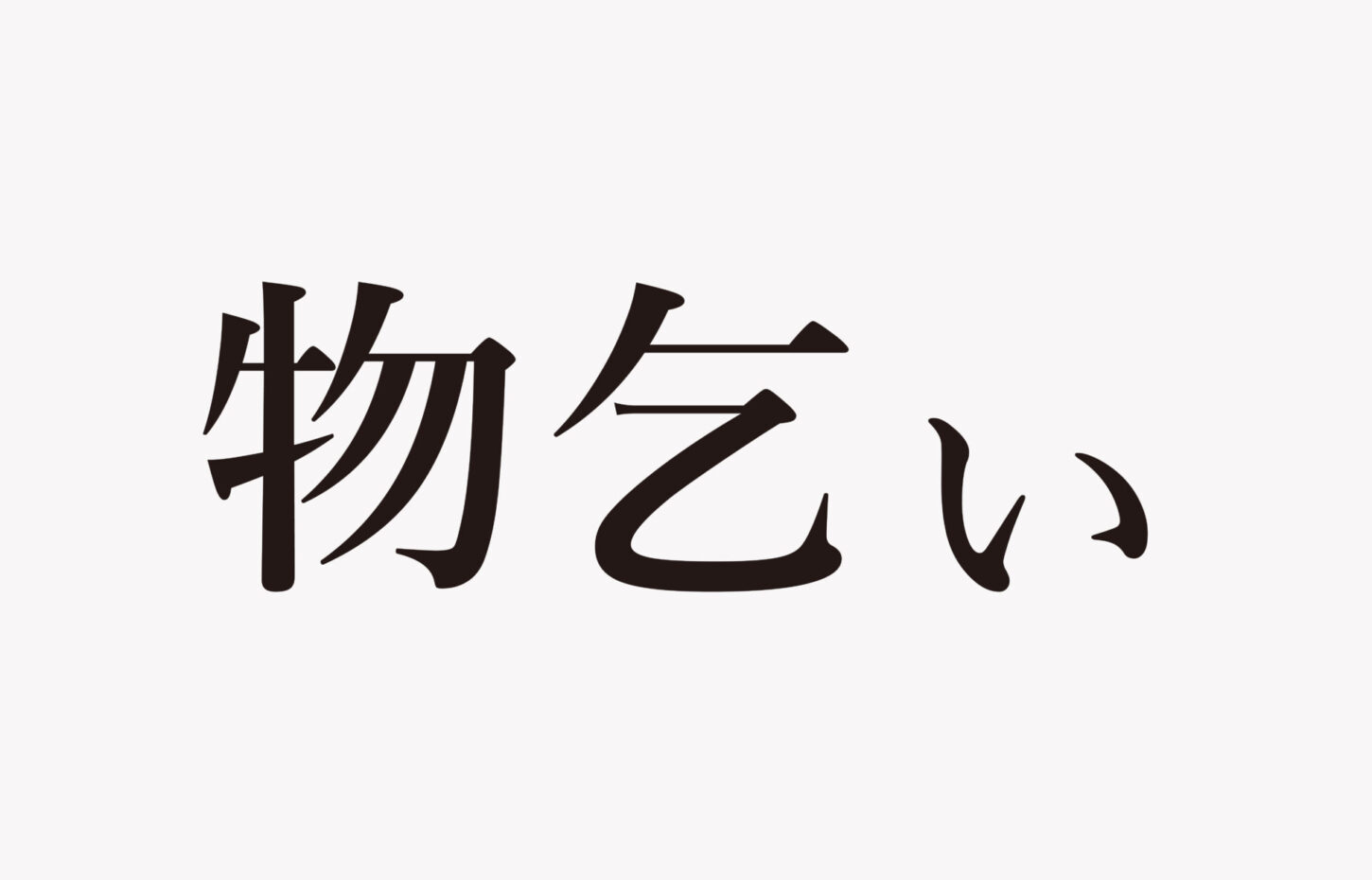
信話集を開いてみると「物乞い」という言葉がときどきでてきます。
例えば~物乞いに信心を教えられた、という話。
まだ初代大先生が商売していた時代、十二月ももうおしつまったころ表に物乞いがきました。気がせいていた初代大先生はつい「こんな猫の手も借りたい忙しいときに、気の利かん奴やなあ」と言葉を荒げて追い払いました。
すると「毎度おおきに」とその物乞いは丁寧に頭を下げて立ち去りました。晩になっても初代大先生の頭からその物乞いの姿が気になって離れません。「あんなこと言わなければよかった。それにしても何にももらえないのにお礼言っていんだな」そしてご自分への反省に思いは行きます。「自分は神さまにお願いして十のうち一つでもおかげがなかったら神さまに文句をいう。とてもあの物乞いに及ばん。ああ今日は物乞いから信心を教えてもろうた。明日来たらこのお礼に二日分やらんならん」
そうしてご信話はここから展開していきます。
信話集で物乞いを通して信心を求めていく話はこればかりではありません。初代大奥様が女の物乞いとの立ち話から信心を身につけていくお話もあります。初代大先生が日常の様々なことから信心を求めていかれたことがうかがわれます。
ですから信話集の展開をいただき私たちの信心に資するべきなのですが、今回はちょっと脱線して物乞いについて話してみたいと思います。
〇お結界で暴言を吐く
以前私がお結界奉仕をしているとき物乞いがきたことがありました。お金が欲しいと要求しました。私は乞われたからといってお結界では少額であってもお金を渡すべきではないと考えます。それで断りました。お金をあげることはできません、とはっきり申しました。
そうするとひどい暴言を口いっぱいしゃべりだしました。気のすむまで暴言を吐いていました。それから何度もやってきてお金をくれといいました。
そのつど私は断り向こうは無茶苦茶言っていました。空腹のようなことを申すので、ご飯ならとあげてみましたが食べ物が目的ではないようで不満そうでした。
酔っぱらってやってきて「どうしても電車賃がいる」とごねたこともありました。帰れないというなら、と僅かな額を渡しました。案の定すぐにお酒を買って飲んでしまったようでした。
こんにちでは初代大先生の時代とは違い社会のシステムで扶助がしっかりと出来上がっています。宗教が教会が、といわれても少なくともお結界は困っている人にお金を渡すところではありません。そして物理的に暴力を振るわなくても口で暴言を吐き続けることは現代ではハラスメントとして成立することでしょう。
にもかかわらず、お結界にやってきては無茶苦茶言って物乞いするひとを私がなぜ止めなかったのか。私には、その人もまた神さまから差し向けられた難儀な人と思えたからです。
おそらく昔なんらかのご縁があってお結界というものを知っていたのでしょう。ならばその人も助かってほしい。こちらも辛抱して接していると段々おとなしくなっていきました。姿がみえないなと感じたら、亡くなったらしいと聞きました。残念でした。神さまが私のお結界でのお取次ぎを磨くために差し向けられたのかな、とも思っています。
(玉水教会 会誌 あゆみ 2025年3月号 に掲載)