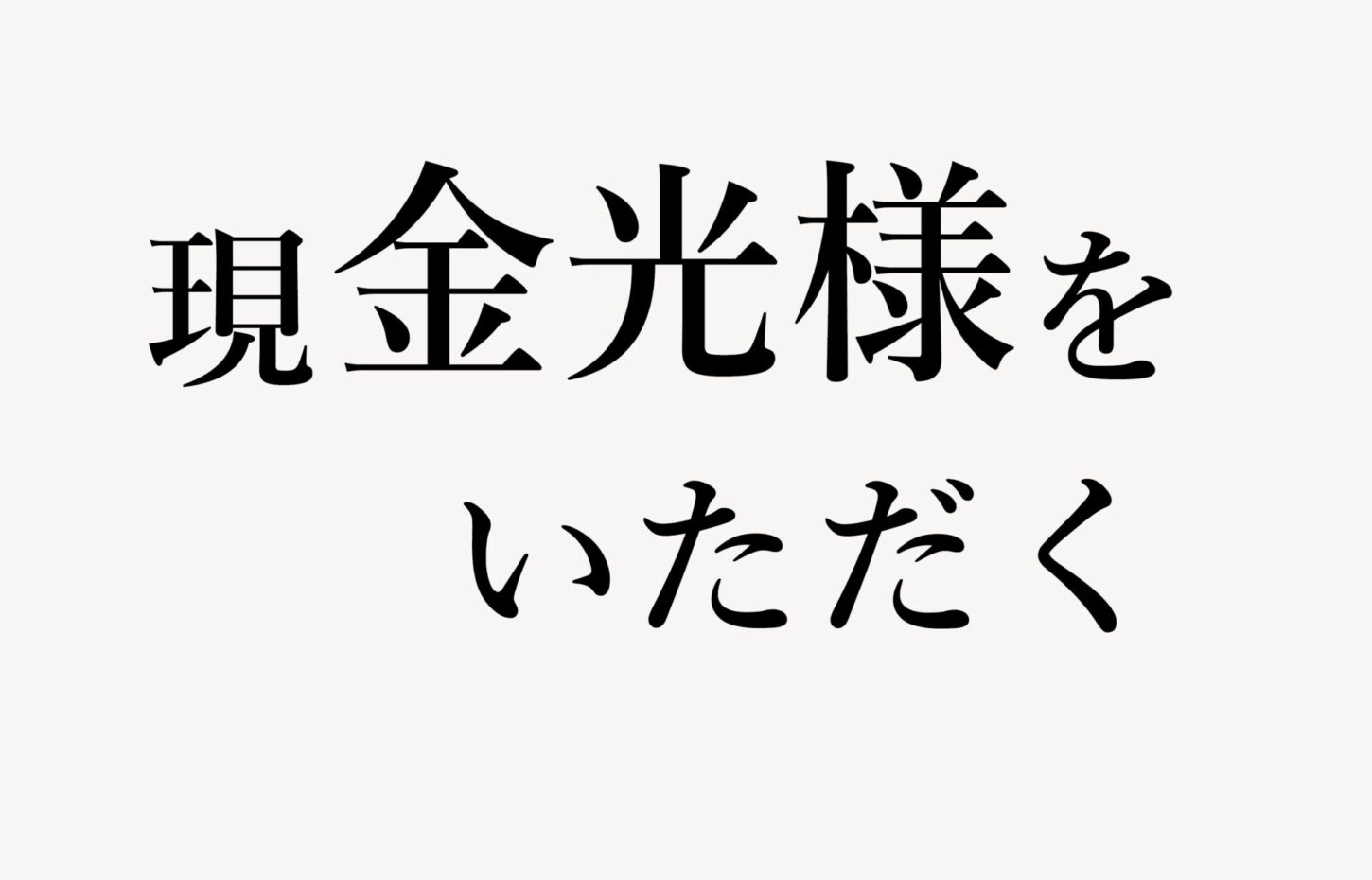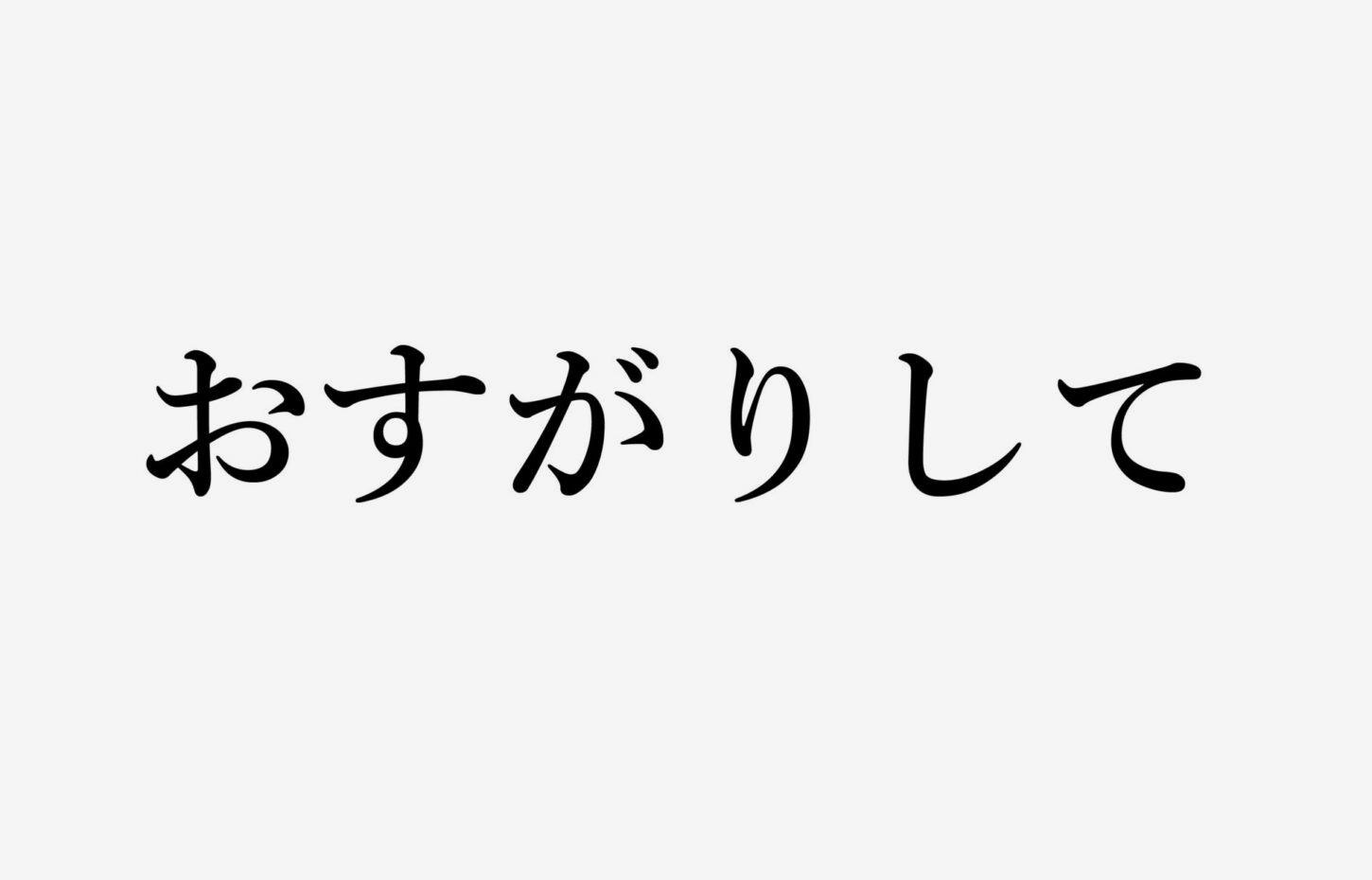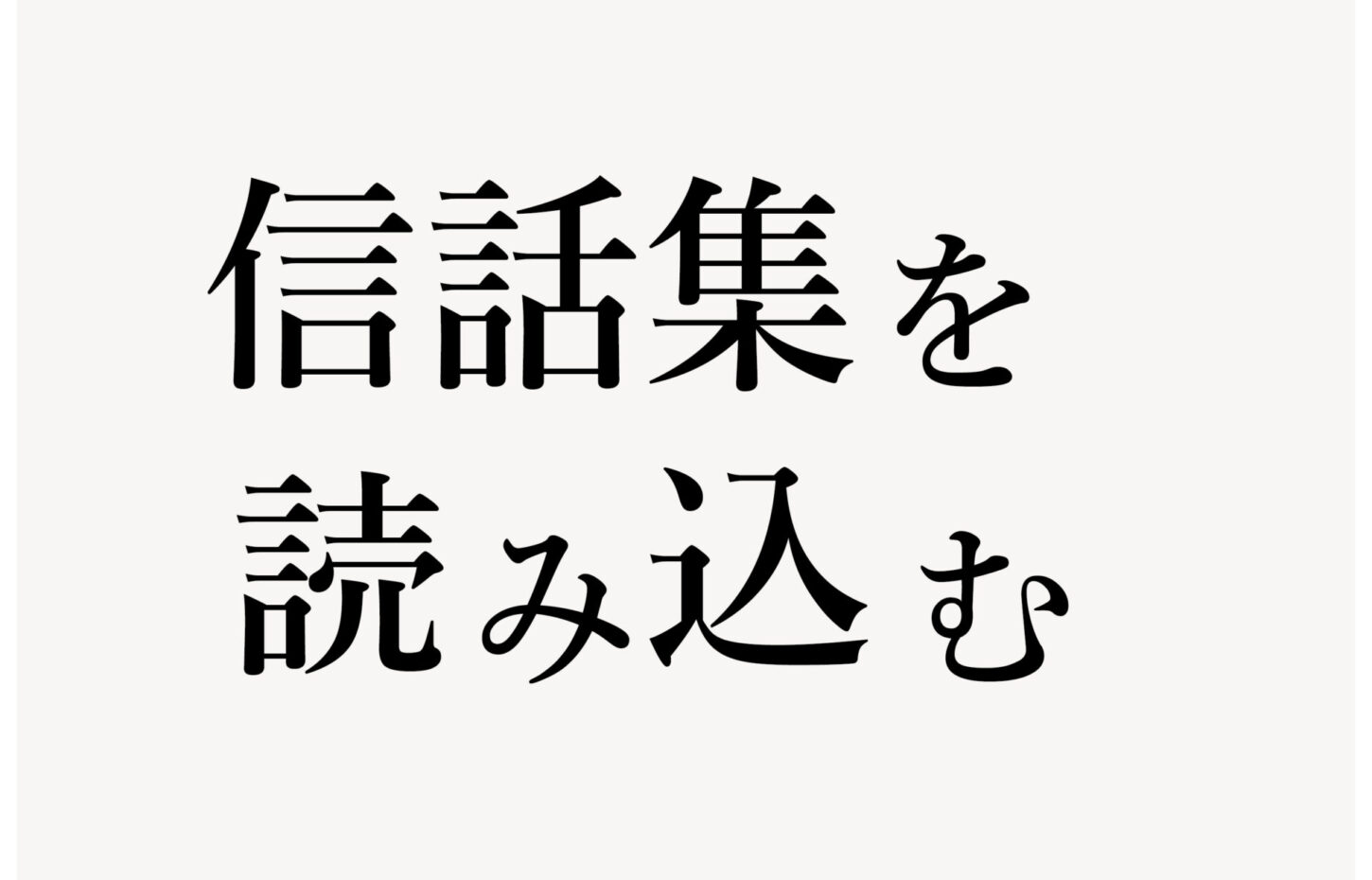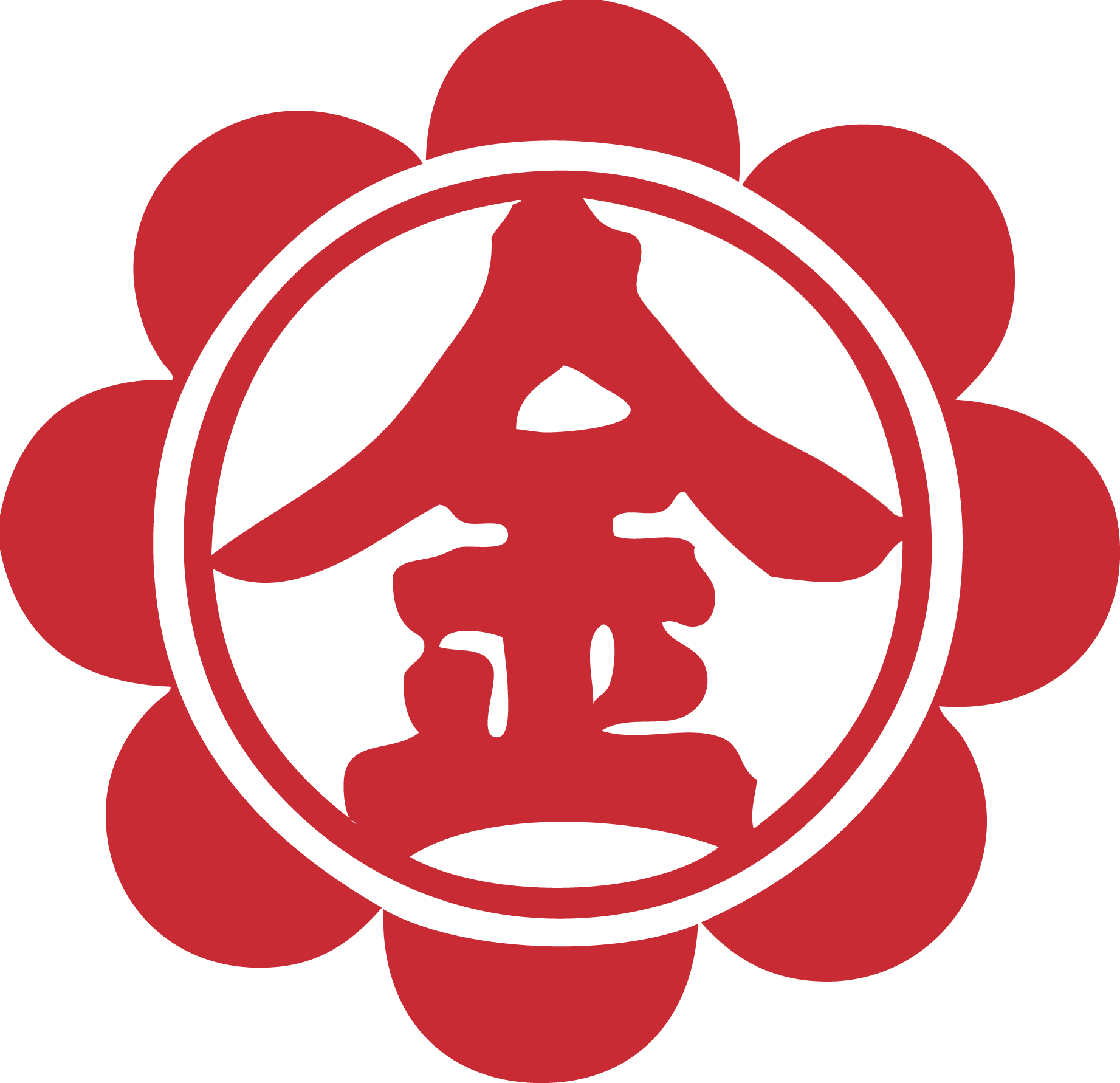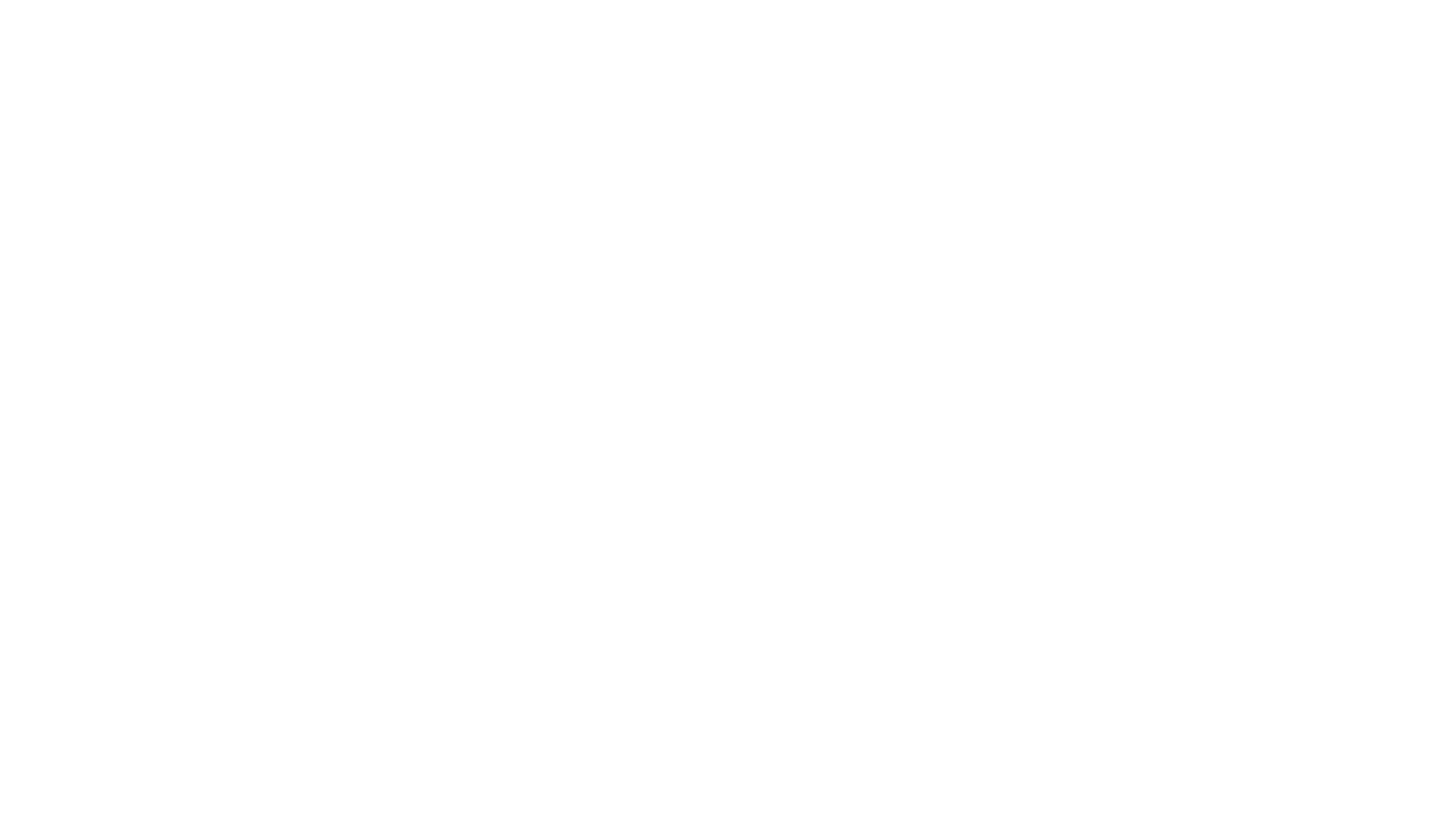おかげ
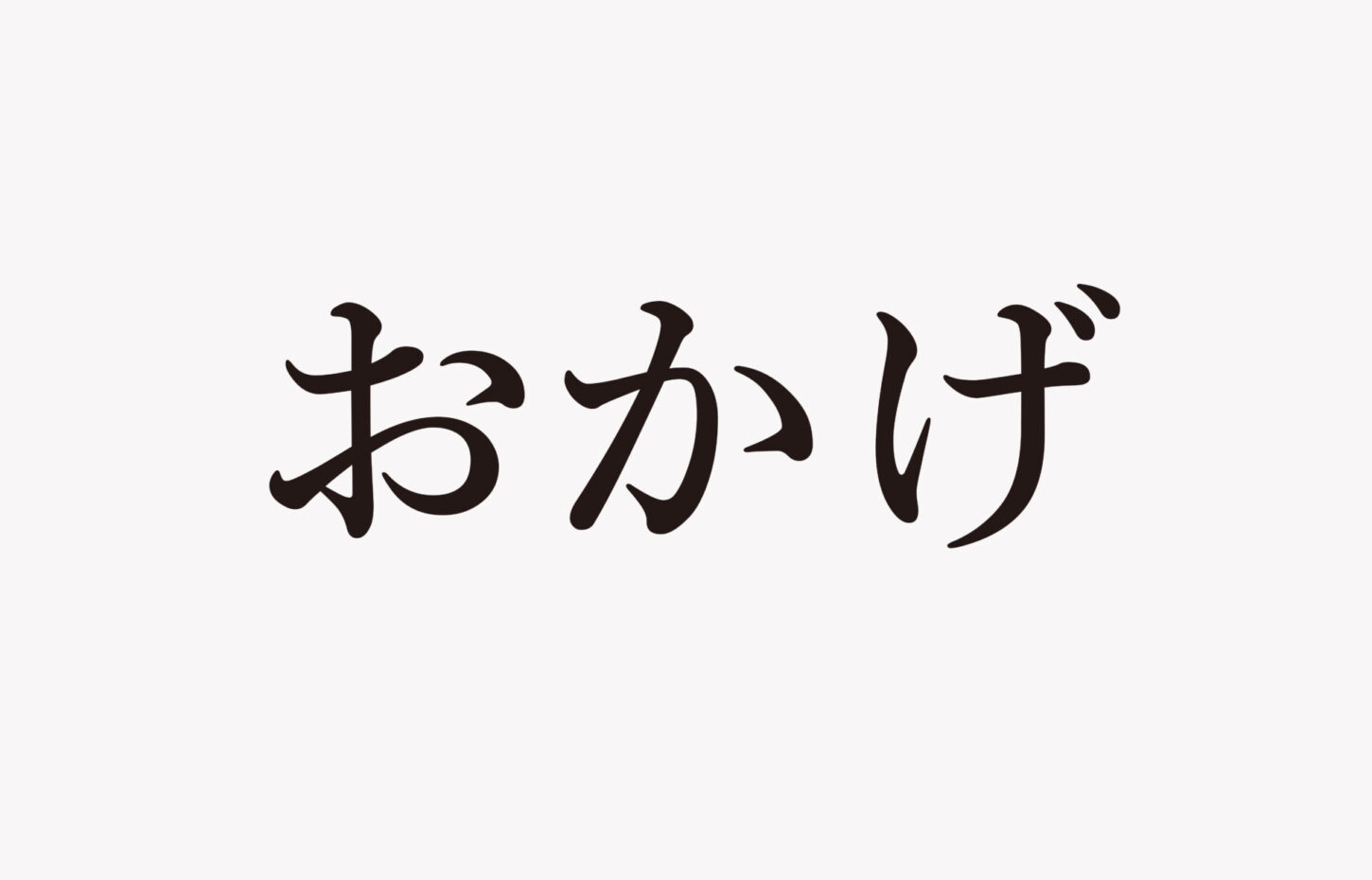
玉水教会は1905年(明治三十八年)創設されました。ことしは布教百二十年になります。いまの教会から北へちょっと行ったところ、土佐堀裏町という場所で、初代大先生は信心仲間とお広前にしようと長屋の一軒を借りていました。
ところが先生がいないということで、責任者の道広教会の先生が三代金光様にお伺いしました。すると「湯川さんにしてもらえ」というお言葉でした。初代大先生は驚いてご本部に参り、お届けしますと「人がかれこれ言えば時期じゃ」と三代金光様はおっしゃいました。そこで初代大先生は教祖奥津城に上がって教祖さまに談判しました。
「私はこれからひと働きして商売でおかげをいただいてそれからお道開きの御用を務めたく思います。しばらくご猶予を」「なんでそんなことをいうのか」と教祖さま。「信心さしていただいたら、物質の面においてもこの通りおかげをいただける、という見本に、二、三百万円こしらえてそれからさしていただきたい」。すると「その方はお金が欲しいのか。そうでなかったら欲しがるものに持たしてやってくれんか」。教祖さまにお言葉に初代大先生は心を決めて布教にいそしむことになられたのでした。
◯「おかげ」から信心を求める
昔は、玉水の信心はおかげ信心だという向きもあったようです。金光教の信心とは清らかな大きい信心なのに、金とか物とか言って下世話だという批判です。商売をして二、三百万円儲けて見本としたい、という言葉などは悪くすればそうとれる。世間のご利益信心ではないか、と。
しかし実際は、逆なのです。
初代大先生は、おかげという事実から信心を求めていくそういうやりかたなのです。
おかげは必ずあるもの、あるに決まったもの。もしお願いして不思議におかげがなかったら、その原因は自分のてもとにある。何か間違ったところがあっておかげがもらえないのです。と初代大先生は説かれます。
この神さまはおかげを授けたくて仕方ない神さまなのです。困った人を見たらどうあっても助けたくて仕方ない。神さまは、一心にといいますか一生懸命お働きくださっている。それでもおかげがないというのは、神さまに問題があるのではなくて、こちらに問題があるのです。そこを考えさせてもらわないといけない。
その”考えさせてもらう”というのがおかげの受けはじめであると私は思うのです。「ああ、なんでおかげいただかれへんのやろか」と考えさせてもらえる。「もらえる」ということがもう既におかげなんです。
そこで分かればいいし、分からなかったら次の機会があります。改めて考えさせてもらうと必ず何かを分からせてもらえるはずです。分からせていただければもっと大きなおかげがいただける、信心はそうやって進んでいくものなんです。神さまは、そういう風に仕向けてくださっているのです。
おかげいただいて、ただ「ありがたい、ありがたい」で終わってしまう。あるいはおかげいただけなかったと神さまに不平を言って終わってしまう。それではもったいないし神さま申し訳ない。信心を進めていく機会を神さまが与えてくださっているのに申し訳ない。
事があったら「これでまた信心を分からせていただける、進めさせていただける」と、前向きに思いをもって一心に願っていく。そうすれば必ずおかげにたどりつけます。
布教百二十年のお年柄、一層のおかげの年にさせていただきましょう。
(玉水教会 会誌 あゆみ 2025年4月号 に掲載)